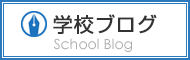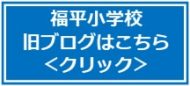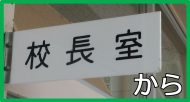校長室から
着任のご挨拶~新たな出会いに感謝~

校長 藤﨑 隆博
校庭の草花に、春の気配が感じられる時節となりました。春休みでひっそりとしていた学校は、新年度のスタートと同時に子供たちの歓声で活気に満ちています。
さて、今年度の定期人事異動で、阿久根市立脇本小学校から参りました第42代校長の藤﨑隆博(ふじさきたかひろ)と申します。福平小学校は、ボランティア活動やプログラミング教育の優れた実績があり、子供たちを支える教職員のチームワークが大変良い学校です。
今年度も、学校教育目標である「『よさ』を生かし、伸ばし合うキラリ輝く福平っ子の育成」の具現化のために、教職員が一丸となり、保護者、地域の皆様との連携を図りながら子供たちを育ててまいります。福平小学校の伝統を受け継ぎつつ、新たな挑戦をしてまいりますので、ご支援・ご協力を賜りますようお願いいたします。
ところで、私が大事にしている信念は、「人は変われる」ということです。最初の職員会議で「春は出会いの季節です。様々な出会いをとおして、人は変わろうとします。よりよく生きようとするものです。この好機に子供に寄り添いながら、全教職員で子供たちを育てていきましょう。」と全教職員に私の思いを伝えました。
1,000人以上の大規模校での勤務は、本校で3校目になります。皆様との新たな出会いに感謝しております。大規模校の特性を生かした学校経営に努めながら、正門横のクスノキのように、子供たちの成長を毎日見守ってまいります。
〝よい子の生活3つの「あ」"
校長 満枝 賢治
本校には生活指導における共通実践事項に〝よい子の生活3つの「あ」"があります。「あいさつ」「あつまり」「あるきかた」です。私は1学期,「あいさつ」の充実を図りたいと考え,職員一丸となってあいさつ指導に取り組んでまいりました。私自身,交通安全指導とあいさつ指導を目的に,毎朝,影原交差点に立ちますが,そこに行く間,すれ違う子どもたちはもちろん,反対側の歩道を歩く子どもたちも大きな声で「おはようございます。」を言えるようになってきました。通学指導員の皆さんからも「6年生が大きな声であいさつしてくれる。こちらが元気をもらっている。」「あいさつをしたあとに,いつもありがとうございますと一言添える子どもがいる。」など,とてもうれしくなる御報告をいただくようになりました。少しずつではありますが,取組の成果が表れてきていると感じています。
さあ,いよいよ夏休みです。地域の中でも子どもたちが元気よくあいさつしてくれることを願っています。中には気付かなかったり,恥ずかしがったりする子どもがいるかもしれません。その時はどうか,保護者,地域の皆様が先手のあいさつに努めていただき,あいさつの飛び交う環境の中に子どもたちを巻き込んでくださるようお願いします。
「令和3年度スタート!」(令和3年4月)
満枝 賢治
この度の定期人事異動により,枕崎市教育委員会から福平小学校にまいりました満枝です。よろしくお願いします。
令和3年度は,本校は児童数1,048人,職員(県費,市費合わせて)67人でスタートしました。「『よさ』を生かし,伸ばし合うキラリ輝く福平っ子の育成」という学校教育目標のもと,「チーム福平」一丸となり,子どもたちを懸命に育ててまいります。
また,「行きたい学校,帰りたい我が家,遊びたい地域」をキャッチフレーズに,学校・家庭・地域の三者協働による教育を積極的に推進したいと考えております。本校の教育活動に対して,御支援・御協力を賜りますようよろしくお願いします。
「たいへんな1年を乗り越えて!」
(令和3年3月)
シンボルツリーの大楠が鮮やかな若葉に身を包む中、新型コロナウイルスへの対応に明け暮れた令和2年度が大詰めを迎えています。
この1年は、子どもたちにとって、楽しみにしていた行事・学習を本来の形で実施できない、本当につらい日々が続きました。「どうして、いつもの運動会ができないんですか?」、「遠足に行きたいです」こういう声が校長室にもたくさん届きました。それらの声に応えることができないまま、中止や縮小の判断をせざるを得ませんでした。心から子どもたちに詫びることの連続でした。
でも、休業が続くことで、学校に行くことの意味・楽しさを知ることができました。我慢を強いられる苦境を嘆くだけでなく、しっかり受け止めて前を向くことの大切さを知ることができました。知恵を絞り工夫すれば、新たなものを生み出すことができることも知りました。できれば経験したくなかった今年の状況ではありますが、子どもたちが得たものもたくさんあると前向きに考えたいと思います。
年度が変わろうとする今、校内を見回すと、これまで学校を支えてきた6年生に代わって朝のボランティア活動を熱心にがんばる5年生の姿があります。朝、笑顔と大きな声であいさつするたくさんの姿があります。教室には、友達と笑顔で語らう姿と「聴き方名人」で授業に臨む姿があります。それらの姿から、「コロナに負けるな」の思いで子どもたちなりにがんばってきたこの1年をしっかり締めくくろうという思いが明確に伝わってきます。このたいへんな1年を乗り越えた子どもたちの更なる成長が本当に楽しみです。
がんばれ、笑顔と「よさ」がキラリ輝く福平っ子!
福平っ子の皆さんへ
~さあ、新学期が始まるぞ~!~
(令和2年4月3日)
おおくすの葉っぱがきれいな緑に変わりました。桜も咲き始めました。新しい先生が着任されました。新しい教室も決まりました。新しい教科書も届きました。みなさんが、1つ上の学年になる準備がしっかりと整っています。あとは、福平っ子のみなさんの登校をまつだけです。
やっと学校に行けるうれしさがいっぱいのみなさんと会えることを、心の底から楽しみにしています。新型コロナウイルスの感染の広がりが心配なので、「体温を計って、ハンカチ・マスクをもって」の約束は守って学校に来てくださいね。
4月6日、みなさんのキラリ輝く笑顔をまっています!
福平っ子の皆さんへ
~このたいへんな事態をみんなで乗り越えましょう!~
(令和2年3月11日)
臨時休校になって、10日が過ぎますね。学校に行けない中で、皆さんがどんなふうに過ごしているのか、とても気がかりです。友達に会えず、一緒に遊んだり勉強したりできないのは、本当にきついでしょうね。
もうしばらく新型コロナウイルスの感染の広がりが落ち着くのを待ちましょう。家の中ばかりで過ごすのもたいへんですから、時には外の空気もすいましょう。そのときには、感染リスクをできるだけ減らすために、風通しが悪くて人がたくさん集まる場所をさけることが大切です。
元気な皆さんの笑顔に会える日が1日も早く来るように、心から祈っています。
「笑顔」で締めくくる3学期に!(令和2年1月)
寒さに負けず元気に登校し、歓声を上げながら校庭を走り回る子どもたちの姿に、3学期が順調に滑り出したことを感じ、うれしく思います。
1月8日の始業式で子どもたちに語ったのが、「笑顔で3学期を締めくくろう」です。人間、いつも笑顔でいることは難しいです。でも、笑顔でいることで周りを明るくし、何より自分自身が前を向く元気をもてる、笑顔にはそういう力があると考えます。「楽しいから笑顔でいるよりも、笑顔でいるから楽しくなる」を大切に、前向きな気持ちで3学期を過ごしていってほしいと思います。
ただ、子どもたちが笑顔でいるには、かかわる大人の役割が大きいことは言うまでもありません。学校と家庭とが一緒になって、子どもの思いをしっかり受け止めながら、子どもたち一人一人が笑顔でいられる毎日をつくることが大切になります。
わずか53日の3学期ですが、1年間の締めくくりに向かって「笑顔がキラリ輝く福平っ子」でいられるよう、職員一丸となって全力を傾注していきたいと思います。
保護者の皆様、地域の皆様、令和2年も福平小、そして福平っ子の見守り・サポートををどうぞよろしくお願いいたします。
「One for all, all for one.」を大切に、みんなで感動を味わう2学期に!
(令和元年9月)
44日間の夏休みを満喫し、様々な体験を通してさらに成長した子どもたちが学校に帰ってきました。学校生活への適応に少し時間のかかっている子どももいますが、ほとんどの子どもが残暑にも負けず、元気に校庭を走り回っています。まずは、スムーズな滑り出しができていることをうれしく思います。
運動会や持久走大会などたくさんの行事がある2学期、子どもたちに大切にしてほしいこととして語ったのが、間もなく我が国で開催されるワールドカップラグビーにちなんだ「One for all, All for one.」です。「一人はみんなのために、みんなは一人のために」と訳されるこの言葉には、ラグビーのチームプレイの精神が込められています。チームの勝利のためにという目標に向かって一人一人が責任を持って役割を果たすとともに、チームが勝つためには、一人でも欠けてはいけない、みんな一人一人が大切な存在だということを伝える言葉です。この言葉の精神は、チームで協力していろいろなことに取り組む子どもたちの学校生活にもつながるものです。
「一人一人がクラスや学年というチームのために、クラスや学年が一人一人のために」、全員が自分の良さを生かしながらチームの一員となって、またチームのみんなが一人一人を大切なチームの一員と考えて、運動会をはじめ、様々な場面で素晴らしい感動を味わい、共に成長する2学期を過ごしてくれることを心から期待します。
自ら命を守る、約束を守る夏休みに!(令和元年7月)
令和の元号発表とともにスタートした1学期が終わりました。この1学期、個々にはいろいろありながらも、1013人の子どもたちが無事に終えたことを素直に喜ぶとともに、子どもたちや学校をあたたかく見守り力強く支えていただいた保護者、地域の皆様に心からお礼を申し上げます。
さあ、44日間の夏休みが始まりました。今年は、熱中症対策として8月1日の出校日をなくしたことから、8月21日までの約1か月、子どもを家庭に返すことになります。
長い休みの気がかりは、何と言っても子どもたちが無事に過ごすこと。その次にくるのが、休み中の過ごし方、なかでもゲーム・インターネットとのつきあい方です。子どもたちには、楽しさ・便利さの陰に潜む様々な危険性に気づく力、判断力は十分ではありません。やはり、そこには保護者の指導と見届けが欠かせません。ネット依存やネットトラブルから子どもたちを守れるのは、まずは保護者です。何より大切なことは、その使い方のルール・約束を親子でしっかり語り、それを守らせることだと考えます。保護者が一方的に決めるのではなく、子ども自身にここまではやる、これ以上はしないという、自分自身の心をコントロールするような約束をし、それをきちんと守らせることを大切にしていただきたいと思います。
普段できないことにじっくりとチャレンジしながら、それぞれのもつ「よさ」がさらに広がる充実した夏休みとなりますように!
一人一人の「よさ」がキラリ輝く福平小に!(平成31年4月)
本校のシンボルツリーである大楠が鮮やかな新緑で子どもたちを見守る中、5月には「令和」と元号が変わる、新しい年度が始まりました。
期待と不安と緊張の中、入学してきた1年生をはじめ、どの学年・学級でも新たな学年のスタートに向けてやる気に満ちた子どもたちの眼差しや笑顔が見られることをたいへんうれしく思います。
さて、今年度、本校は、学校教育目標を次のように変えました。
「よさ」を生かし、伸ばし合うキラリ輝く福平っ子の育成
子どもたちは、どの子も「よさ」をもっています。その「よさ」は、成長とともに増える・磨かれるものであり、他者に見出されるものでもあります。
子ども同士がお互いに友達の「よさ」を探す行為は、その友達に関心を寄せることであり、相手を大切な一人の仲間として認めることであり、さらに思いやりや優しさをもつことです。また、見つけてもらった側も自分に関心を向けてもらえた喜び、「よさ」を見つけてもらえたことへの感謝、そして自分に対する自信を身につけていきます。「よさ」を知り、認めてもらうことによって、「自分にはよさがある」という自信や自己肯定感、「自分は役に立っている」、「必要とされている」という自己有用感、さらに未来に向かってよりよい自分であろうと努力する向上心が育まれると考えます。また、他者とのかかわりを通して、それぞれの「よさ」を認め、伸ばし合う過程を経て、相互の信頼関係やつながり、絆を生み出すなど、集団の高まりにもつながることを期待しています。この一人一人が備える「よさ」に着目し、「よさ」に気づくこと、生かすこと、伸ばすことを学校経営の中心に据え、教育活動を展開していきたいと考えます。
今年度の福平小は、学級数40(うち、特別支援学級10)、児童数1、015人でスタートしました。その子どもたちに対して、総勢67名の職員が一丸となって、「キラリ輝く福平っ子」の育成に、全力を注いでまいります。これまで同様、保護者の皆様のご理解とご協力、そして、地域の皆様のバックアップをどうぞよろしくお願いいたします。